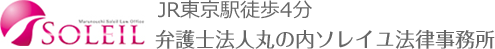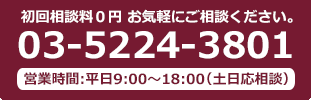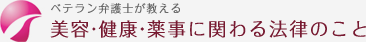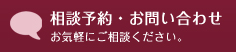- 2016.10.21
-

- ツイート
課徴金の制度に関する法律を立案した方々によると、この3パーセントは、消費者庁が設置された平成21年以降、不当な表示が行なわれ、措置命令が出された事案での事業者の売上高営業利益率を計算したところ、その中央値が3パーセントであったため、この数字を採用したとのことです。
売上高営業利益率とは、営業利益を売上高で割ったものですが、経済産業省のホームページ[1]を見ますと、少し古いデータですが、中小企業、大企業とも4%程度の数字となっています。売上高営業利益率は、一般的に、小売業者では低く、不動産や医薬品会社では比較的高いとされており、課徴金の金額を計算するのに、一律3パーセントとすることは、公平ではないようにも思われますが、業種別に割合を変えることは煩雑であり、行政の効率を考えると一律に3パーセントと決めたことも合理性があるものと思われます。
なお、小売業界は、売上高営業利益率が低い業界であるといわれており、不当な表示が行なわれた商品の売上高の3パーセントの課徴金を支払うと、手元に残る利益はほとんどないか、場合によってはマイナスとなる可能性もあります。
不当な表示で得た収益はすべて課徴金として支払わせ、事業者に利益を残さないようにしようという法律の意図が3パーセントという数字からは明らかになっています。
The following two tabs change content below.


弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。
最新記事 by 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム (全て見る)
- 【令和6年7月】株式会社キャリカレに対する景品表示法に基づく措置命令について弁護士が解説 - 2024年7月24日
- 【令和6年6月】医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令 - 2024年6月11日
- 【令和6年5月】中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について解説 - 2024年5月29日