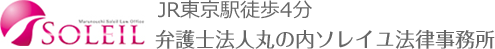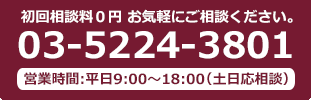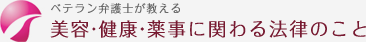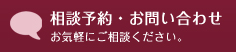- 2021.6.29
-

- ツイート
商品を買ったときに、「おまけ」がついてきたら嬉しいですよね?もし高価なおまけがついてくることが約束されていたら...商品ももちろん大事ですが、おまけにつられて商品本体を買ってしまうということもありえるのではないでしょうか。実は、そのような状態を規制するための法律があるのです。今回は、景品表示法(以下、「景表法」といいます。)における景品類規制について、お話します。
景表法とは
景表法上の「景品類」とは、①顧客を誘引するための手段として、②事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する、③物品、金銭その他の経済上の利益のことを言います(景表法2条3項)。
景表法では、これらの景品類に該当するものについて、A総付景品、B一般懸賞、C共同懸賞という類型に分類した上で、提供できる限度額を設定しています。そして、その限度額を超えて景品類を提供した場合には、行政が措置命令を出すなどして、景品類の提供を禁止することなどができます。
景品はいくらまで大丈夫?
肝心の分類とその限度額ですが、一定の条件に該当する者全員に物品を提供する場合、「A総付景品」に該当します。
そして、「A総付景品」の場合、取引価額が1000円未満の場合は景品類の最高額は200円まで、取引価額が1000円以上の場合は景品類の最高額は取引価額の10分の2まで、という制限があります。「A総付景品」の具体例としては、「先着○名様にもれなく○○プレゼント」というようなものがあり、このパターンが最も多いです。
次に、くじやコンテストによって当選者や価額を定める場合、「B一般懸賞」に該当します。
そして、「B一般懸賞」の場合、取引価額が5000円未満の場合は、景品類の最高額が取引価額の20倍とされ、取引価額が5000円以上の場合は、景品類の最高額は10万円とされています。なお、景品の総額については、取引価額にかかわらず、懸賞に係る売上予定総額の2%までという制限があります。「B一般懸賞」の具体例としては、抽選券を商品に同封し、抽選で数名に景品が当たるといったものがあげられます。
そして、多数の事業者が共同して懸賞を行う場合、「C共同懸賞」に該当します。
この「C共同懸賞」の場合、取引価額にかかわらず、景品類の最高額は30万円、景品類の総額は懸賞に係る売上予定総額の3%とされています。「C共同懸賞」の具体例としては、商店街のイベントが考えられます。
化粧品モニターの場合は?
では、景表法においてこのような景品類の規制がある中で、化粧品のモニター募集をした場合に、謝礼を渡すということは認められるのでしょうか?
今般、口コミサイトを運営したり、メーカーが自社の宣伝をしたりするに当たり、モニターを募集するということが多く行われています。その際、モニターには、商品サンプルを渡すこととなり、そのサンプルを使ってもらって口コミを投稿してもらうこととなりますが、サンプルとは別に、謝礼を渡すことは認められるか、事業者としては気になるところです。
ここで、景表法上の「景品類」の定義に戻りましょう。
口コミサイト運営者にとって、募集するモニターは、いわゆる顧客とは異ります。また、メーカーがモニターを募集する場面を想定しても、モニターは純粋な顧客とは異ります。そうしますと、そもそも①顧客を誘引するための手段としてという要件(顧客誘引性)がありませんので、景表法上特段問題はないこととなります。
景表法規制対象外の例
また、少し脇道に逸れた話になりますが、実は、「5個買った人は、100円引き」といった値引きや、アフターサービスについては、景表法の景品類規制の対象から外れます。
このとき、先程紹介した「A総付景品」と混同しやすいのですが、実質的に同一の商品・サービスであれば、値引きととらえ、規制対象から外れるとされています。
そのため、例えば、「コーヒーを3杯飲んだら、1杯無料券プレゼント!」というような場合も、4杯分のコーヒーを飲んだとしたときに1杯分が安くなっている、というように整理し、トータルで少し安くなった、すなわち値引きがあったということで、規制から外れることとなります。
その上、「景品類」の定義をよく見てみると、②事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する(取引付随性)という要件がありますが、これに当たらない場合は、当然「景品類」ではなくなりますので、景品類の規制からも外れることとなります。
具体的には、ウェブサイトなどで、商品の購入や来店を条件とせず、ウェブサイト上から申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画については、景品類規制がかかりません。このような企画は、オープン懸賞と呼ばれています。
このように、一見して、景表法上の規制がかかりそうに思えるものでも、よくよく検討してみれば特段景品類の規制にかかることなく実施できる企画もありますので、事業者の皆様におかれましては、いろいろとアイデアを絞ってみてはいかがでしょうか。
広告表現にお悩みの方は薬機法に詳しい丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士にご相談下さい
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は2009年に創業いたしました。2016年、弁護士業界ではいち早く美容健康分野に対するリーガルサービス提供を開始し、現在では健康博覧会、ビューティーワールド ジャパン、ダイエット&ビューティーフェアでの薬機法セミナー講師を務めるなど、美容健康業界の広告適正化に向けての啓蒙活動を行っている法律事務所でございます。
これでは何も訴求できない、どんな風に書けばいいのかわからないーそのようにお悩みの方、企業の販促・プロモーション・広告担当の方、弊所は法律に則った訴求表現のアドバイスもさせていただくことが可能ですのでぜひ一度ご相談ください。
広告は文章だけでなく、広告全体から判断されます。
若返り系のワード以外にも、ビフォーアフター写真のような若返りを暗示する写真やイラストでの表現も薬機法違反の対象となりますので注意が必要です。
弊所では美容広告に詳しい弁護士が多数在籍しており、皆様のご不安に寄り添うことができます。
丸の内ソレイユ法律事務所の広告審査は、スポットでA4 1枚/11,000円からご依頼頂けます。(1枚単価がお安くなる顧問プランもございます)
全て弁護士がチェックしており、グレーな部分は行政へ確認を取ってからレポートをお戻ししております。
ネットで調べても何が正しいか分からない!自社内で審査すると時間がかかる!と広告表現についてお悩みのお客様は、是非一度弊所をご活用いただければ幸いです。
>>お問い合わせ・お見積りはこちらから(初回相談30分無料・広告データも送信できます)
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
最新記事 by 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム (全て見る)
- 「エイジングケア」という言葉は広告に使えるか?(令和5年3月最新版) - 2023年3月28日
- 薬機法において、医療機器の製造・販売・輸入で注意すべき点は?弁護士が解説 - 2022年1月31日
- 美顔器の広告は薬機法で規制される?使用可能な表現とは - 2022年1月28日