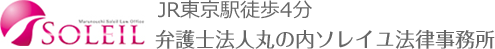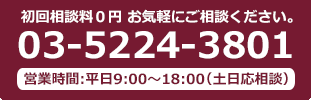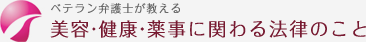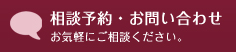1.「広告」とは?
1-1 広告該当性の要件
薬機法では未承認医薬品等の「広告」が禁止されているわけですが、そもそも何が「広告」に該当するのでしょうか。
広告該当性を判断するための要件は、「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」(平成10年9月29日 医薬監第148号)(都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医薬安全局監視指導課長通知)により定められている以下の3点です。
①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること(誘因性)
②特定の商品名が明らかにされていること(特定性)
③一般人が認知できる状態であること(認知性)
1-2 特定性について
広告該当要件のうち、特に問題になるのが2点目の特定性です。
特定の商品名が載っていなければ、薬機法の規制対象である広告には該当しません。そのため、商品名を明らかにしなければ、商品に含まれる成分について医薬品的な効能効果を説明しても、そもそも広告ではないのですから薬機法に違反しません。これを成分広告と呼んだりします。
しかし、事業者が成分広告をする最終的な意図は、その成分を配合している自社商品のPRするため、という場合が少なくありません。そのため、成分広告を自社商品の広告(商品広告)と何とか関連させようとするのですが、両者の関連性が強すぎると、商品広告と成分広告が「2つで1つの広告」と判断されてしまい、特定性があるものとして薬機法違反の広告となってしまうことがあります。
これまで、「2つで1つの広告」と判断されたパターンを3つご紹介します。
【パターン1 バイブル商法】
パターン1は、雑誌のページ①にある商品(商品A)の広告を掲載し、別ページ(雑誌ページ②)に商品Aに含まれる成分(成分B)の効能効果を記載する、という方法です。

【パターン2 検索誘導】
パターン2は、ある商品(商品A)のページ(ウェブページ①)に「●●で検索」と記載し、商品Aに含まれる成分(成分B)の効能効果を記載したウェブページ②に誘導する、という方法です。

【パターン3 リンク】
パターン3は、商品Aに含まれる成分(成分B)の効能効果を記載したウェブページ②に、ある商品(商品A)の広告が記載されたウェブページ①のリンクを載せる方法です。

広告表現にお悩みの方は薬機法・景表法に詳しい丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士にご相談下さい

対面販売など、クローズドな環境での広告は、広告に該当しないという判断になる可能性がありますが、情報が会社から一歩外に出たら、インターネットなどの多くの人の目に触れる可能性があるのなら、その情報は広告となる可能性が高くなりますのでご注意ください。
また、最近弊所によくご相談があるのは、売りたい商品のページには効能効果は出さず、別で立てたメディアサイトにその商品の効能効果の根拠となる論文や成分データを掲載する手法。
このような商品と効能効果ページを切り離して広告する手法は薬機法に違反しないか、というご相談です。
これは貴社の販売する商品と成分ページがどう結びつくかが焦点となってきます。成分ページと商品広告が一体とみなされないよう注意を払う必要がありますので、どういったスキームで商品を広告、販売していけばよいかご心配な方は是非丸の内ソレイユ法律事務所へご相談下さい。
これでは何も訴求できない、どんな風に書けばいいのかわからないーそのようにお悩みの方、企業の販促・プロモーション・広告担当の方、弊所は法律に則った訴求表現のアドバイスもさせていただくことが可能です。
広告は文章だけでなく、広告全体から判断されます。
近年、景品表示法に基づく措置命令や課徴金納付命令が多く出されており、ナンバーワン表記や二重価格表示、そして「飲むだけで痩せる!」などの事実と異なる表記への取り締まりが一層強くなっているのが現状です。
加えて、美容健康業界の企業様は、事実に反する表示での景表法違反にも注意ですが、よくご質問を頂くアンチエイジング系の若返りワードや、肌色を変える美白系のワード、ビフォーアフター写真のような若返りを暗示する写真やイラストでの表現も薬機法違反の対象となりますので注意が必要です。
弊所では広告・プロモーション法務に詳しい弁護士が多数在籍しており、皆様のご不安に寄り添うことができます。
丸の内ソレイユ法律事務所の広告審査は、スポットでA4 1枚/11,000円からご依頼頂けます。(1枚単価がお安くなる顧問プランもございます)
全て弁護士がチェックしており、グレーな部分は行政へ確認を取ってからレポートをお戻ししております。
ネットで調べても何が正しいか分からない!自社内で審査すると時間がかかる!と広告表現についてお悩みのお客様は、是非一度弊所をご活用いただければ幸いです。
>>お問い合わせ・お見積りはこちらから(初回相談30分無料・広告データも送信できます)
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
最新記事 by 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム (全て見る)
- 「エイジングケア」という言葉は広告に使えるか?(令和5年3月最新版) - 2023年3月28日
- 薬機法において、医療機器の製造・販売・輸入で注意すべき点は?弁護士が解説 - 2022年1月31日
- 美顔器の広告は薬機法で規制される?使用可能な表現とは - 2022年1月28日