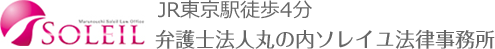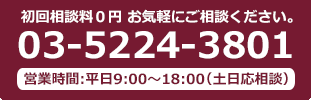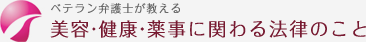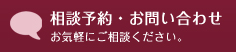消費者庁は、サプリメントや健康食品等を販売する通信販売業者である株式会社オルリンクス製薬に対し、令和6年4月9日、特定商取引法の規定に基づき、3か月間の通信販売業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)の停止、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずること等の指示を命じるとともに、同社の代表取締役に対し、3か月間、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む)の禁止を命じました。
消費者庁「特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(3 か月)及び指示並びに当該業者の元代表取締役に対する業務 禁止命令(3か月)について」(https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_240410_01.pdf)
通信販売業者の義務
今回、行政処分の根拠となったのは、特商法上、通信販売業者に課される次の表示に関する規制です。
⑴ 誇大広告等の禁止(特商法12条)
通信販売業者が広告を行う場合、商品の性能や、契約の解除等に関する事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないこととされています。
⑵いわゆる最終確認画面における表示義務
通信販売においては、申し込み完了することとなる、いわゆる最終確認画面において、商品等の販売価格や、支払時期・方法、契約の解除に関する事項をはじめ、一定の事項について表示することが義務付けられています。
問題となった行為(特商法12条の6)
今回、具体的に消費者庁が上記規制に抵触すると判断したのは、次のような表示でした。
 消費者庁ホームページより https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_240410_01.pdf
消費者庁ホームページより https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_240410_01.pdf
⑴誇大広告等の禁止
オルリンクス製薬は、販売する定期購入契約の商品について、広告上は「24時間365日自動音声で解約可能」、「限られた時間内でしか解約の出来ない不便さは一切ありません 面倒な手続き・解約阻止の説得などもゼロ」 等と表示していました。
一方、実際の契約解除方法は、まず解除できる時期につき、消費者の商品受領後、一定の期間に限られており、さらに、解除の方法としても、電話問合せの上、URLからメッセージアプリの専用アカウントに登録 (友だち追加)して、当該アカウントのトークルーム内で氏名等を入力することで本人確認を行い、その後、エントリーフォームで最低15文字以上の記入が必要なものを含め、10問以上の質問への回答の入力をしなければならず、その上で、オルリンクス製薬において、当該エントリーフォームに入力された内容を確認して、その結果連絡を消費者がメッセージアプリで受け取ることにより解除が完了するという、煩雑な手続を経る必要がありました。
上記のような広告について、消費者庁は、あたかも、簡易な手続により契約を容易に解除できるかのように示す表示をしていた一方、契約を容易に解除できなかったとして、誇大広告違反と指摘したわけです。
⑵いわゆる最終確認画面における表示義務
オルリンクス製薬は、いわゆる最終確認画面において、解約方法に関する上記の契約条件につき、その一部しか表示していませんでした。
具体的には、最終確認画面上では、解約希望の場合、「商品をお受け取りいただいた後、次回の発送日の14日前までにお客様ご自身にて【オルリンクスオートメーションサポート(解約・休止専用窓口)】までご連絡を頂き、案内にしたがってLINEにて解約・休止の申請をしてください。」との表示程度しか行わず、そのほかの解約に関する条件については「詳しい解約手続はこちら」として別のページを引用する方法をとっていたようです。
かかる表示をもって、消費者庁は、最終確認画面における表示義務に違反があるものと判断しました。
特商法12条による摘発について
特商法12条に関しては、先月に初の摘発事例が出たところであり、これに引き続き景表法ではなく、特商法によって摘発がされました。
No.1表示が問題となった前回の摘発事例と異なり、今回のケースは、解約手続に関する表示が問題となったケースであり、景品表示法の有利誤認表示としても摘発が考えられたと思料されますが、課徴金の納付命令の可否等も含め、消費者庁は特商法による摘発を実施したものと思われます。
参考記事:
https://www.health-beauty-soleil.jp/%e5%88%9d%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%95%86%e6%b3%9512%e6%9d%a1%ef%bc%88%e8%aa%87%e5%a4%a7%e5%ba%83%e5%91%8a%ef%bc%89%e9%81%95%e5%8f%8d%e3%81%ae%e4%ba%8b%e4%be%8b%ef%bc%88%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc/
最終確認画面における表示義務について
最終確認画面に関する表示については、消費者庁から、以下のガイドラインが出されており、どういった表示を満たせば適法な表示といえるかの指針が示されています。
そのため、ECサイトを開設・運営するにあたっては、このガイドラインを参照することが必要です。
消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20220601la02_07.pdf)
特に最終確認画面は、サイト作成上の都合で、表示できる文章量、スペースが限られるということがあると思います。そのような限界からか、最終確認画面の表示を順守していない業者も見受けられます。
しかし、まず、ガイドラインでは、すべての条件を最終確認画面それ自体に列記することまでは求めておらず、リンクを設けて、リンク先に詳細を明記する方法や、別ウィンドウに詳細を記載する方法でも差支えないこととされています。
したがって、通販事業者としては、こういった方法も駆使して、適法な表示を行う必要があります。
但し、注意が必要なのは、解約条件については、解約方法を特定の手段に限定する場合、とりわけ、消費者が想定しないような限定がなされる場合や、消費者が申込みをした際の手段に照らして当該消費者が容易に手続を行うことができると考えられる手段での解約連絡を受け付けない等の場合には、リンク先や参照ページの表示に委ねるのではなく、最終確認画面においても明確に表示することが必要であると、ガイドライン上、示されていることです。
解約条件が消費者の保護、トラブル防止に重要なものであることから、特に解約に煩雑な手続を求めたり、解約方法を限定したりする場合には、その点を消費者が明確に認識できるよう明示的な記載が求められているといえます。
今回処分を受けたオルリンクス製薬も、「詳しい解約手続きはこちら」として、リンクを使用することで、解約条件を別途表示していたように見受けられますが、同社の解約条件のような煩雑な手続を求めるものについて、そのような表示をしていたとしても、最終確認画面における表示として不十分であると判断されたものと思料されます。
消費者庁は、近時、NO.1表示との関係でも、活発に処分を出している状況です。
ECサイトの開設・運営にあたっては、表示事項の適法性を維持できるよう、弁護士のリーガルチェックを受けるなどの対応をおすすめします。
広告表現にお悩みの方は薬機法に詳しい丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士にご相談下さい

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は2009年に創業いたしました。2016年、弁護士業界ではいち早く美容健康分野に対するリーガルサービス提供を開始し、現在では健康博覧会、ビューティーワールド ジャパン、ダイエット&ビューティーフェアでの薬機法セミナー講師を務めるなど、美容健康業界の広告適正化に向けての啓蒙活動を行っている法律事務所でございます。
これでは何も訴求できない、どんな風に書けばいいのかわからないーそのようにお悩みの方、企業の販促・プロモーション・広告担当の方、弊所は法律に則った訴求表現のアドバイスもさせていただくことが可能ですのでぜひ一度ご相談ください。
広告は文章だけでなく、広告全体から判断されます。
若返り系のワード以外にも、ビフォーアフター写真のような若返りを暗示する写真やイラストでの表現も薬機法違反の対象となりますので注意が必要です。
弊所では美容広告に詳しい弁護士が多数在籍しており、皆様のご不安に寄り添うことができます。
丸の内ソレイユ法律事務所の広告審査は、スポットでA4 1枚/11,000円からご依頼頂けます。(1枚単価がお安くなる顧問プランもございます)
全て弁護士がチェックしており、グレーな部分は行政へ確認を取ってからレポートをお戻ししております。
ネットで調べても何が正しいか分からない!自社内で審査すると時間がかかる!と広告表現についてお悩みのお客様は、是非一度弊所をご活用いただければ幸いです。
広告審査サービス紹介ページはこちら
>>広告審査チェック
>>お問い合わせ・お見積りはこちらから(初回相談30分無料・広告データも送信できます)