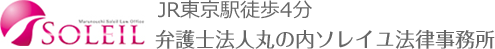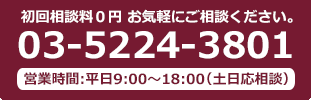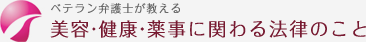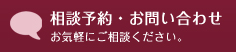消費者庁は、令和6年7月19日、株式会社キャリカレに対し、同社が提供する通信講座について、景品表示法に基づく措置命令を行いました。
今回は、消費者庁は、どういった理由で措置命令を行ったのか、今後、どういった点に注意していけばよいのか、解説していきたいと思います。
措置命令の内容
今回の措置命令のポイントは、2点あります。
まず一点目としては、いわゆる二重価格表示(通常の販売価格と実際の販売価格を併記することで安さを強調する表示)をしていた場合の「通常価格」が実際に提供された実績のない価格であったというものです。二重価格表示を見た消費者としては、販売価格が通常価格より安いため、これを機に商品又はサービスを購入しようと考えることになります。この通常価格が実際には販売実績のない架空の価格であれば、通常より安い価格とはいえないので、消費者を安いと誤信させて購入を誘引していることになります。
次に二点目としては、期間限定のキャンペーンとして割引価格を表示していたところ、実際には、期間経過後も割引価格で販売していたというものです。期間限定キャンペーンでの割引価格を見た消費者としては、期間経過後には価格が通常価格に戻るため、割引価格が適用されるキャンペーン期間中に商品又はサービスを購入しようと考えるわけです。これが、キャンペーン期間経過後も割引価格で購入できるのであれば、あえてキャンペーン期間中に購入しなくてもよいわけで、消費者を誤信させて購入を誘引していることになります。
以上のとおり、今回の措置命令のポイントとしては、二重価格表示をしている場合の通常価格が存在しない価格であったという点と、期間限定のキャンペーンにおいて、キャンペーン経過後も割引価格で表示していたというものになります。
事実と異なる表示になっていないか注意
二重価格表示については、消費者庁が公表している「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方(価格表示ガイドライン)」により、考え方が詳細に示されております。特に、過去の販売価格を比較対象価格として表示をする場合には、①セール開始時点の過去8週間において、比較対照価格での販売期間が過半以上であること、②その価格での販売期間が2週間未満でないこと、③その価格で販売された最後の日から2週間以上を経過していないこと、といった基本的なルールがあります。こうしたルールに反する運用になっていないか、注意が必要です。
また、期間限定に限らず、「●●限定」といった表示については、事実異なる表示になっていないか注意が必要です。
まとめ
今回の措置命令の内容は、二重価格表示やキャンペーン期間経過後の割引価格での販売といった、過去にも頻繁に行われているものでした。基本的な内容ではあるのですが、二重価格表示や期間限定キャンペーンは、消費者に対する訴求効果も高いため、どの事業者も実施している施策であるとともに、消費者庁も厳しく取り締まっている類型の一つかと思います。
これを機に、二重価格表示やキャンペーンの施策を見直してみるとよいでしょう。